御所野遺跡の復元と実験
土屋根建物の復元
土屋根建物の発見
平成8年(1996年)、遺跡西側で焼けた建物跡の調査が行われました。そのうち最も炭になった木材が良好に残っていた中型の竪穴建物跡と大型の竪穴建物跡を確認しました。これまで縄文時代の竪穴建物は、茅葺き屋根で復元されていましたが、この竪穴建物跡に関しては、茅が確認できず、焼けた木材の上に焼けた土が載っている状態で見つかったため、屋根に土が載っていたことがわかりました。

焼けた建物の跡
復元図の作成と実験復元
平成8年(1996年)9月、焼けた竪穴建物跡の調査をもとにして建築史の専門家である浅川滋男氏(奈良国立文化財研究所-当時)から復元図を作成していただきました。この図は同じ奈良文化財研究所の西山和宏氏が現場で出土炭化材の図面を作成し、それにもとづいて作成しています。
平成9年(1997年)8月、復元図をもとにして中型の土屋根建物を実験的に復元しました。

竪穴建物復元図

実験復元
焼失実験
平成11年(1999年)10月、土屋根建物を復元してから2年後、実際の燃え落ちかたを調べるために焼失実験を実施しました。
竪穴内は酸欠状態になりやすいため、事前に天窓とその周囲を取り除き、開口部を広く開けてから各柱に設置した薪にいっせいに点火しました。
5、6分で床上の薪が炎上、20分後には天窓周辺の屋根が崩落しました。その後、ときどき酸欠状態となって消えそうになったり、勢いよく燃える状況が続きました。屋根が落ちて空気が入ってくると壁板が勢いよく燃え、中には内側に倒れこむものも確認されました。このようなことが繰り返され、1時間後にようやく火が消えました。
実験後の燃えた竪穴建物跡は風化状況を確認するため、そのまま現地に保存しています。

焼失実験のようす
土屋根建物の復元
御所野遺跡では、これらの実験や調査をふまえ新たな図面を作成し、竪穴建物を復元しています。
竪穴建物は、それぞれの建物が発掘された場所に盛り土をして、その直上に復元しています。竪穴の大きさや柱の位置、太さも発掘された建物跡にもとづいて復元し、復元した後も屋根の土をたたいて締めたり、炉に火を入れたりするメンテナンス作業や調査・実験を通じて本来の縄文時代の姿に近づけていく作業を行っています。

竪穴建物復元

竪穴建物火入れ作業

屋根たたき
掘立柱建物の復元
掘立柱建物の発掘調査
遺跡中央部の配石遺構の外側には多くの柱穴を確認しており、東側から西側、さらに北側では主に6本柱の建物がいくつかあったことが判明しています。このような建物は地面に直接穴を掘って柱を埋め込んでいるため、掘立柱建物と呼ばれています。
建物の大きさは、大型のもので短軸3メートル前後、長軸6メートル前後、小型のものは短軸が2メートル前後、長軸が4メートル前後となっています。柱穴の大きさはいずれも直径が60センチメートルから80センチメートル、深さが90センチメートルから140センチメートルとなっていました。

掘立柱建物の発掘
復元図の作成
建物は高さ2メートル弱に床を張り、アイヌの建築様式であるケツンニ(アイヌ家屋の基本系と考えられる三脚構造で、単独だとテント式の丸小屋、2つ以上だとその間に棟木を渡して「チセ」となる)を両端に建ててその間に棟を載せた樹皮葺き屋根を想定しました。

掘立柱建物復元図
掘立柱建物の復元
掘立柱建物は遺跡中央部で5棟、そのほか東ムラで1棟を復元しました。中央部の建物は配石遺構、あるいは墓にともなう施設と考えられ、東ムラの建物は、隣接する竪穴建物にともなう施設として荷台状の建物として復元しました。
いずれの建物もそれぞれ発掘された場所に盛り土をして、その上にベースを作って復元しています。柱の太さ、位置も竪穴建物同様、発掘された建物跡に基づいて設置しています。

ケツンニ構造

掘立柱建物の復元風景
縄文時代の技術の復元
石斧による木の伐採実験
遺跡から出土した石斧をもとにして道具を作成し、クリの木の伐採実験をしました。木は縄文時代の竪穴住居で使用する径30センチメートルから80センチメートルのものを伐採しています。

復元した石斧

伐採実験のようす

伐採後
木製工具による土の掘削
縄文時代の遺跡から出土した木製品の中から、竪穴住居の建築で使用されたものを復元し実験を行っています。

木製掘削具

掘削実験のようす

掘削後
縄文里山づくり

縄文人が生活の糧を得るために、手を加えて作りあげた環境を「縄文里山」といいます。
御所野遺跡では、最近の調査で明らかになった縄文人の活動を体験しながら、縄文人の生活と当時の環境を復元する「縄文里山づくり」を行っています。

屋根たたきのようす

火おこしのようす

どんぐりの実

どんぐりの植栽

中央ムラの畑

西ムラの畑
里山でとれる材料
-
木 住居の建築、燃料となる薪づくり、道具づくり
-
樹皮 屋根材、容器づくり、繊維からの縄づくり、布づくり、薬
-
蔓 容器づくり 布づくり、実の利用(マタタビ、サルナシ、ヤマブドウ、サンカクヅル、キイチゴ、エゾニワトコ)
-
笹 容器作り、屋根材
-
石 石器(御所野遺跡周辺から採取できるもの、流通による搬入品)、石製品(装飾品)
-
粘土 土器づくり、土製品(装飾品)
-
草など 食用の山菜、薬用植物、実の利用(クリ、コナラ、トチ、クルミ)
里山での作業
-
森の散策
-
木の実から苗づくり、植栽管理
-
枝拾い、枝下ろし
-
木の伐採、薪づくり、木の加工、家づくりの材料、道具
-
季節毎の山菜取り、山菜の加工
-
木の実などの採取、あく抜き
-
蔓などの採取、素材作り 、森の草刈り
ムラでの作業
-
家づくり、家の修理
-
土屋根の雪下ろし
-
土屋根の叩き締め
-
竪穴住居のなかでの火起こし、火燃やし
-
縄文食作り
-
かご作り、土器づくり、石器づくり
-
ムラの草刈り、草取り
| 体験名 | 内容 | 申込方法 | 体験期間 |
|---|---|---|---|
|
火おこし体験 〈無料〉 |
マイギリ式という方法で火をおこします。 3人一組で体験していただきます。 |
5日前までにお電話にてご予約ください。 |
4月から10月 |
|
自然と遊ぼう体験 〈無料〉 |
公園内の植物などを観察します。 オオイタドリの笛や竹とんぼ、ビュンビュンごまなどを自然の素材でつくって遊びます。 |
5日前までにお電話にてご予約ください。 |
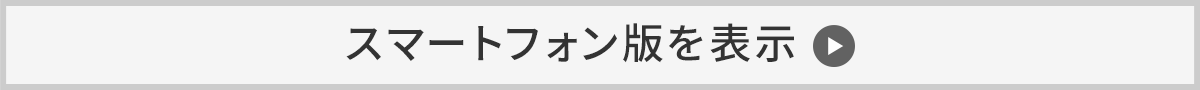






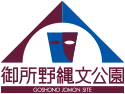
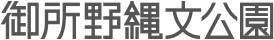
更新日:2023年05月17日